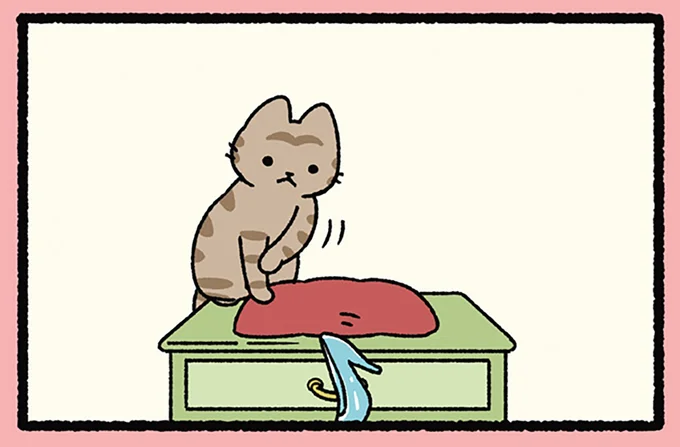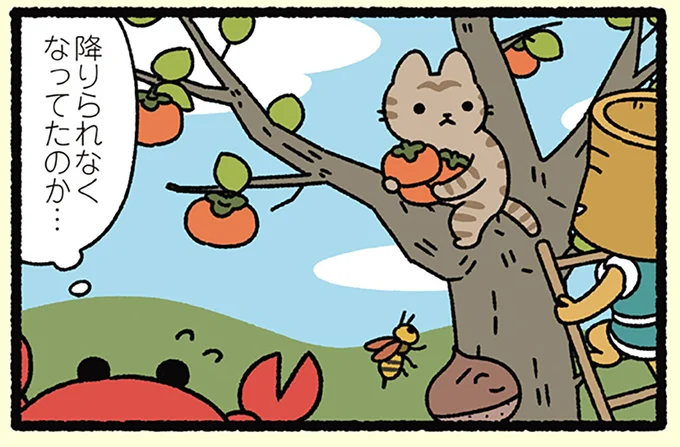余命は1カ月どころか週単位…70代女性がよろめく体を奮い立たせてやった驚くべき行為と奇跡的に生きた年月

■亡くなる前にもう一度両親の墓参りをしたい
病気が重くなり動けなくなりますと、人は若い頃を追憶し、故郷に帰りたいという想いが強くなるようです。
亡くなる1週間くらい前、人によってはもっと前から、少なからぬ人にせん妄という混乱が生じます。現状の認識が困難になり、時間や場所の感覚があいまいになるのです。
そのような混乱の最中に、昔のことを語りだす人が少なからずいます。昔と今を取り違えてしまっているのです。息子を父だと勘違いしたり、妻を母と勘違いしたりすることもあります。
私は、100歳近い女性患者さんに「お父さん」と泣き叫ばれて抱きつかれたこともあります。彼女は私に、父の姿をみたのでしょうか。
そういった患者さんたちの様子をみるにつけ、幼い頃の記憶というのはいかに強固に心に残っているか思い知らされます。人は意識していなくても、心の奥底には、幼少期に住んでいた場所、そこで共に生きた人々のことが記憶として刻まれているのでしょう。
死ぬ前に「故郷に帰りたい」「両親の墓参りをしたい」という想いを強くする人もいます。

余命が週単位と思われるほど衰弱した、70代の女性患者さんがいました。
その方は望郷の想いから、なんと飛行機に乗って1000km以上も離れている故郷に帰ったのです。これが最後だと知ったうえでの、文字通り覚悟の旅でした。
彼女は故郷に眠る父母の墓に手を合わせたそうです。また兄弟と忌憚なく笑い合い、心の中ではっきりと別れを告げたそうです。
そのうえでよろめく体を奮い立たせて、また1000km以上もの飛行機の旅をして、帰ってきました。
もはやまともに歩くのも困難なほどの状態でしたから、この往復は奇跡的な旅路だといえると思います。
しかし、その後に起こったことこそが、奇跡と呼ぶべきでしょう。
死出への道となると思われた旅は、予想もしない未来を切り開くことになったのです。なんと彼女は、その後1年近く生きたのです。旅立つ前に、複数の医師から余命が週単位の可能性が十分あると診断されたのに。
余命わずかと知ったとき、彼女の中に強い衝動として生まれたのは、遠く離れた故郷に帰り、今は亡き両親に挨拶に行くことだったのです。そのとき、彼女の体に、力強い命の杭が打たれたといえるでしょう。
自分の成り立ち、自分のつながり、それらを取り戻すことは、明らかに生命力に息吹を吹き込むことになる。それを実感させられました。
■故郷で家族に囲まれ安らかな最期を
故郷に行くことや墓参りをすることは、しばしばプラスの影響を与えると思います。また、故郷で最期を迎えたいと思う人もいます。
私が京都の病院に勤務していたときのことです。余命が週単位である患者さんとかかわりました。今一番気になっていることを聞くと、「故郷の鳥取で最期を迎えたい」と訴えてきたのです。
私は頭を抱えました。ホスピス・緩和ケア病棟の入院には、長い待ち時間が必要なこともよくあります。鳥取の緩和ケア病院に紹介しても、数週間ほど待たされる可能性が高い。鳥取への転院を待っている間に、京都で死亡する可能性があるのです。
予想通り病院探しは難航しましたが、幸い即断で彼女を受け入れてくれるという医療機関が見つかりました。患者さんは翌日転院を果たしました。
その後、何週間も連絡がありませんでした。忙しさにかまけて彼女のことが記憶から薄れてきた頃に、転院先の緩和ケア病棟から連絡がきました。患者さんの死の連絡です。
しかし彼女の鳥取での生活は、幸せなものだったようです。到着するや否や、たくさんの家族・親族が彼女を取り囲みました。彼女の周囲には笑顔が絶えることなく、それは死の瞬間まで続いたそうです。
彼女は故郷に包まれ、孤独がやわらぎ、強固な家族の絆を取り戻して、逝ったのです。当初診断されていた余命よりも長い頑張りをみせたのは、故郷や家族・親族のパワーゆえでしょう。
故郷への想いを実現できた方の例を紹介しましたが、一般に終末期になってから旅をしたり、遠方に転院したりするのは、容易ではありません。健康なうちに実行に移すべき。体が動かなくなってからでは、遅いのです。
■終末期になって実感仕事人間の辛い思い
仕事ばかりの人生だったことを、終末期になって後悔する人もいます。仕事専従が当たり前の時代に働いていた世代では、趣味が少なかったと嘆く人は少ない印象ですが、団塊の世代よりも若い世代には、趣味のひとつやふたつも持っていればよかったなあとしみじみ語る方がいます。
仕事しか引き出しがないと、仕事ができなくなったときに辛い思いをする可能性が高くなるかもしれません。
終末期のために趣味を持つ必要はありませんが、何かを追求し続けるのは、人生の引き出しを増やし、己の糧となるのではないかと感じます。その趣味が最期まで、人を支え続けるものにもなるのです。
糖尿病になったことを機に、10kmの散歩を日課とした男性がいました。それまでは「仕事命」で散歩などしなかったのですが、「自然が美しいと、初めて気づいた」と楽しさを知ったのです。さすがに距離は短くなりましたが、散歩は末期がんになっても続け、闘病生活を豊かにしてくれました。
多くの患者さんは入院すると、「することがない」と嘆きます。でも私が出会った50代女性の患者さんは、そんな悩みとは無縁で、病床で粘土細工を作っていました。
最初の作品は、1羽のフクロウでした。フクロウは数が増え、いつしか家族となっていきました。そのフクロウを妹さんが焼き上げると、独特の光沢をもつ美しい置物に仕上がったのです。フクロウ家族は病室の片隅に鎮座し、彼女を見つめていました。
彼女にはまだ10代の子供が2人いました。画用紙にさらさらと筆を走らせ、子供たちの絵を描きました。
死の数日前まで、彼女の創作意欲はほとんど衰えませんでした。出来上がった作品は、家で彼女の夫や子供たちを今も見守っていることでしょう。
■家族との間の思い残しはなくす
私が死ぬときに後悔することに関する本を出版した後のことです。出版社が読者に「死を前にして何に後悔するか」というアンケートを取ったところ、家族関連についての解答がとても多かったのです。家族や大切な人との間での思い残しは、多いのかもしれません。
家族に「愛している」と言うのに抵抗を感じる人もいるでしょうが、ならば「ありがとう」と言ってほしい。私はそう思っています。
横倉秀二さん(仮名)という70代後半の患者さんがいました。某大学の教授を務めたこともあり、性格は気難しい方と評判でした。大腸がんの手術を勧められても、断固拒否。がんが進行し、お腹も腹水がたまって膨れるようになりましたが、「僕は病気じゃない!」と言い張るのでした。
やがて嚥下も困難となり、誤嚥性肺炎を起こしたのです。
横倉さんは出身地の秋田に兄と妹がいるそうですが、常々「家族に連絡をするな!」と言っていました。事情はわかりませんが、数十年も会っていないそうです。しかしこの状態ではと、皆で悩み話し合った末に、お兄さんに連絡をしました。
翌日、80代になるお兄さんが病院を訪ねてきました。すると、呼吸状態も悪かった横倉さんに元気が出てきたのです。小康状態になったこともあり、お兄さんはいったん秋田に帰りました。

1カ月経ち、2カ月が経ち、横倉さんの病状が悪化。再びお兄さんに連絡を入れました。
病床で兄の姿を認めた横倉さんの瞳から、一筋の涙がこぼれ落ちました。
翌朝、お兄さんが、「先生、秀二がね、『ありがとう』と言ってくれたんですよ。悪態ばかりついていた秀二が。嬉しかったです」
横倉さんが亡くなったのは、それから数時間後。安らかな死に顔でした。
※本稿は、雑誌『プレジデント』(2024年8月16日号)の一部を再編集したものです。